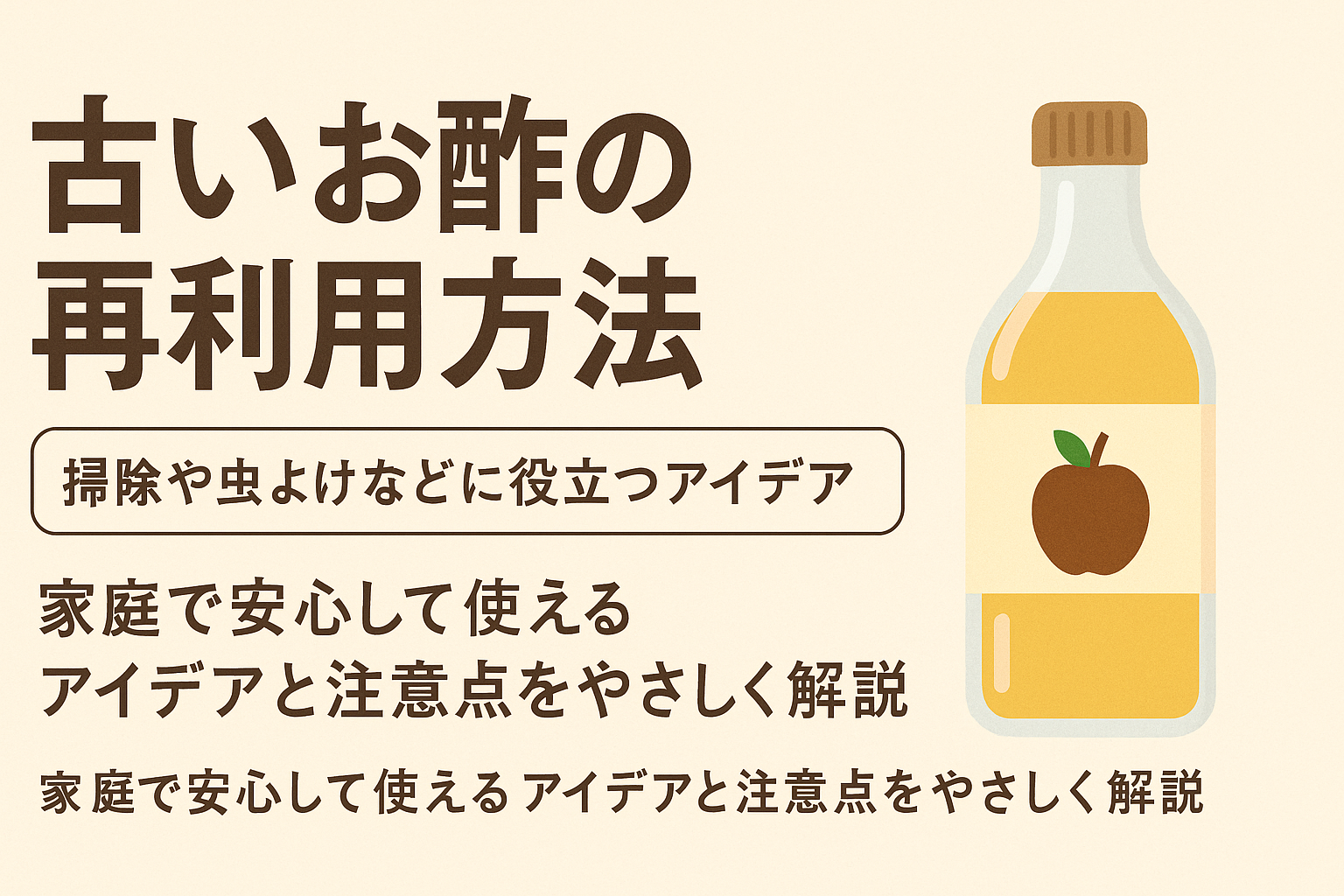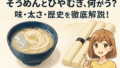「土用の丑の日にはうなぎを食べる」──そんな習慣、誰もが一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?
でも、そもそも「なぜうなぎなの?」「丑の日って何?」と疑問に思ったことはありませんか?
この記事では、そんな素朴な疑問に答えるべく、土用の丑の日の由来や意味、江戸時代に始まった歴史的背景をわかりやすく解説しています。
また、うなぎが苦手な方のために“う”のつく代替食や、現代の楽しみ方についても詳しくご紹介。
知っていると誰かに話したくなる、ちょっとした雑学もたっぷり詰まっています。
「なるほど、そういうことだったのか!」と納得できる内容を、ぜひ最後までお楽しみください。
江戸時代に始まった「うなぎを食べる習慣」
夏にうなぎが売れなかった?!
「土用の丑の日にうなぎを食べる」という風習が、いつ・どのようにして始まったのかをご存じでしょうか?
実はこの習慣、江戸時代に始まったと言われています。当時の夏、気温が高く食欲が落ちる人が多い季節に、うなぎのようなこってりした食べ物はあまり売れなかったようです。冷蔵庫のない時代ですから、保存も難しく、衛生面にも気を使わなければなりませんでした。そんな背景のなか、夏の売り上げに悩んでいたうなぎ屋が、ある人物に相談を持ちかけたのです。
平賀源内が仕掛けたPRとは?
相談を受けたのは、発明家として知られる平賀源内(ひらがげんない)。彼は学者でありながら、今で言う広告プランナーのようなセンスも持ち合わせていました。源内は「丑の日に“う”のつくものを食べるといい」という言い伝えに目をつけ、これをマーケティング戦略として活用。「本日、土用の丑の日 うなぎの日」という貼り紙を作成し、店先に掲げるよう提案したのです。
なぜ「丑の日」に注目したのか
“丑の日”は、十二支の一つ「丑(うし)」にあたる日で、約12日周期で巡ってきます。昔の暦は、干支を日付に使っていたため、「今日は“丑の日”」という感覚が人々の生活の中に根づいていました。また、「う」のつく食べ物を食べると元気が出る、夏を乗り切れるという言い伝えもあり、それをうまく利用した源内のセンスは、まさに時代を先取りしたものでした。
江戸の町で広まった“うなぎブーム”
この貼り紙は江戸の町で話題になり、多くの人が「じゃあ丑の日はうなぎにしようか」と考えるようになりました。あくまで言い伝えに乗っかった「きっかけ」ではありますが、暑い時期に特別なものを食べて季節を感じる、という行為が人々の暮らしにフィットしたのかもしれません。こうして“うなぎブーム”は起こり、他のうなぎ屋も真似をするようになり、瞬く間に文化として定着していきました。
習慣が現代にまで定着した理由
うなぎは日本独自の食文化の一つとして成長し、その後の時代にも脈々と受け継がれてきました。関東風と関西風で調理方法が違うことからもわかるように、地域ごとの特色も発展しています。また、江戸の人々が「暑い日にしっかり食べる」という考え方を重視したことも、今の私たちが「夏の土用の丑の日にうなぎを食べる」という習慣を続けている理由かもしれません。
「う」のつく食べ物は縁起が良い?
食文化としての“う”のつく食べ物の意味
「土用の丑の日=うなぎ」という印象が強いですが、実は昔から「“う”のつく食べ物は縁起が良い」とされてきた文化があります。これは、「丑(うし)の日」にかけて、「“う”のつくものを食べると良い」と考えられていたことに由来しています。
つまり、うなぎだけでなく、“う”が頭につく食べ物であれば、縁起物として扱われていたのです。
この風習の背景には、昔の人々の生活習慣や知恵が関係しています。現代のように医療や栄養学が発達していなかった時代、夏の暑さで体調を崩す人も多く、季節の変わり目を乗り切るための知恵として、食べ物に願掛けをする文化が自然と根づいていきました。
どんな「う」のつく食べ物がある?
では、うなぎ以外にはどんな食べ物があるのでしょうか?代表的なものをいくつかご紹介します。
| 食べ物 | 特徴と理由 |
|---|---|
| うどん | のど越しがよく、冷やしても美味しい夏の定番 |
| 梅干し | 昔から常備されていた保存食で、おにぎりにもぴったり |
| 瓜(うり) | キュウリやスイカなど、体を冷やす夏野菜として親しまれてきた |
| 牛肉 | “う”で始まり、スタミナがつくごちそうとして食卓に登場 |
| うに | 高級食材として特別感があり、丑の日にふさわしい |
どれも日常の食事に取り入れやすく、特別な日でなくても楽しめるものばかりです。「“う”がついていればなんでもOK」という柔軟な考え方は、日本の食文化の豊かさを物語っていますね。
言葉遊びから生まれた“験担ぎ”
「“う”のつく食べ物を食べるといい」という考え方は、科学的根拠というよりも、“ことば遊び”や“験担ぎ(げんかつぎ)”に近いものです。日本人は昔から、語呂合わせや音の響きに意味を見出す傾向があります。「くじに勝つために“カツ丼”を食べる」「風邪をひかないように“ねぎ”を首に巻く」といった、ちょっとした迷信も同じような発想です。
このように、「丑の日=“う”のつく食べ物」という文化も、遊び心と祈りの気持ちが込められた習慣だったのです。
地域によって異なる「う」の食文化
日本全国を見渡すと、土用の丑の日に食べるものにも地域差があります。例えば、関西ではうなぎよりも「うどん」を中心にした家庭料理が楽しまれることもあるそうです。また、山梨県では「う」のつく野菜を複数使った煮物を作る風習がある地域もあります。
こうしたローカルな食習慣は、全国共通の行事であっても、それぞれの地域に根ざしたスタイルで親しまれている証拠です。
現代にも息づく“う”の食文化
今でも、スーパーのチラシや店頭ポップで「“う”のつく食べ物で元気に!」といった言葉を見かけることがあります。SNSでも「#丑の日ごはん」などのハッシュタグで、さまざまな“う”の料理が投稿されています。
うなぎだけにこだわらず、自由な発想で「この日はちょっと特別な食事を」と工夫する気持ちは、今の時代にもぴったり。食べ物を通じて季節を感じ、家族や友人と一緒に楽しむことが、何よりのごちそうなのかもしれませんね。
土用の丑の日とはそもそもどんな日?
「土用」って何?意外と知られていない意味
「土用の丑の日」と言われても、「そもそも“土用”ってなに?」と聞かれて答えられる人は意外と少ないかもしれません。
“土用”とは、実は日本の暦(こよみ)に由来する言葉で、季節の変わり目にあたる特別な期間を意味しています。
具体的には、「立春・立夏・立秋・立冬」という四季のはじまりの前、およそ18日間ずつの期間が“土用”と呼ばれています。
その中でも、特に注目されるのが「夏の土用」。これは、立秋の前、つまり真夏にあたる7月中下旬ごろの時期を指します。
この時期は暑さのピークで体調を崩しやすく、「季節の節目に備えて体を整えよう」という意識が古くからありました。
そうした背景から、“土用”は単なる暦の言葉というだけでなく、健康や生活のリズムを見直す時期として位置づけられていたのです。
「丑の日」は十二支の一つ
“丑の日”とは、干支(えと)のひとつ「丑(うし)」が日にちに割り当てられた日のことです。
干支というと、年賀状などでなじみのある「子・丑・寅・卯…」の12種類が思い浮かびますが、実はこれ、年だけでなく“日”にも使われていたんです。
つまり、「丑の日」とは、12日ごとにやってくる“丑”に当たる日のこと。
ですので、土用の約18日間の間には、最低でも1回、多い年は2回の“丑の日”が巡ってくることになります。
“土用の丑の日”とは、要するに「土用という季節の節目にある“丑の日”」という意味なのです。
年に何回ある?“二の丑”って?
よく「今年は土用の丑の日が2回ある!」という話を聞くことがありますが、これはどういうことなのでしょうか?
土用の期間は約18日あるため、その間に丑の日が2回来ることもあります。1回目を「一の丑」、2回目を「二の丑」と呼び、これは干支の並びによって自然に決まるものです。
年によっては、「7月25日が一の丑、8月6日が二の丑」など、10日ほど間をあけて2回登場することがあります。
この場合、多くの家庭ではどちらか一方を「うなぎの日」として選ぶこともあれば、両方にちなんで別の“う”のつく食べ物を楽しむこともあります。
「今年は丑の日が2回ある!」なんて話をすれば、ちょっとした話題にもなりますね。
なぜ“夏の土用”だけが有名?
土用の丑の日は年に複数回ある可能性がありますが、なぜ「夏」だけが特別視されるのでしょうか?
これは、夏の土用が一年の中で最も体調を崩しやすい時期と考えられていたためです。特に江戸時代の日本では冷房も冷蔵庫もなく、真夏の暑さは今よりも厳しく感じられたでしょう。
そのため、「この時期にこそ特別な食事をして体をいたわる」という意識が強く働いていました。
その象徴として定着したのが、“丑の日にうなぎを食べる”という文化だったわけです。
また、うなぎの旬が秋から冬にかけてであることから、夏場にうなぎの消費を促すための商業的な意味合いもあったと考えられています。
暦と暮らしをつなぐ日本の知恵
昔の人々は、暦の動きと自然のリズムをうまく生活に取り入れていました。
農作業の計画、健康管理、衣替えなども、すべて暦をベースに行われていたのです。
「土用の丑の日」も、そうした伝統的な知恵のひとつ。季節の移り変わりを感じながら、暮らしに寄り添う行事として今も息づいています。
行事の意味を理解して取り入れるだけで、ちょっとした日常が少し豊かになる。そんな日本ならではの暮らしの知恵を、次の世代にも伝えていきたいですね。
うなぎが苦手でもOK!おすすめの代替食
うなぎが苦手、または手が出ないという人も多い時代
「土用の丑の日=うなぎ」と言われても、実際には「うなぎは苦手なんだよね…」とか「高くて買えない…」という声もよく耳にします。
うなぎは特別感のある食材ですが、年々価格が高騰しており、気軽に食卓に並べるにはハードルが高くなっているのも事実です。特に国産うなぎは1尾数千円することもあり、家族全員分を用意するのはなかなか大変。
また、味の好みや、アレルギー、宗教的な理由などでうなぎを避ける人も一定数います。
そんな中でも、「土用の丑の日を楽しみたい!」という気持ちに応える方法がたくさんあるのです。
“う”のつく食べ物を楽しむという選択肢
うなぎ以外の“う”のつく食べ物で、気軽に季節の行事を楽しむのも、ひとつの良い方法です。
実際に昔から親しまれている食材を以下のようにまとめてみました:
| 食べ物 | 特徴・おすすめの食べ方 |
|---|---|
| うどん | 冷やしても温めてもおいしい。夏場は冷やしうどんが人気 |
| 梅干し | ごはんのお供やおにぎりに。さっぱりした味で夏向き |
| 瓜(うり) | キュウリ・スイカ・冬瓜など。水分が多く、旬の野菜として人気 |
| 牛肉 | 焼き肉や牛丼など、がっつり系のメニューにも対応可能 |
| うに | 寿司ネタとしてだけでなく、クリームパスタにも相性抜群 |
こうした“う”の食材は、家庭でも手に入りやすく、料理のアレンジもしやすいのが魅力です。「“う”がつく食べ物ならなんでもOK!」という柔軟な発想で、行事をもっと自由に楽しんでみましょう。
スーパーやコンビニでも手軽にGET!
最近は、スーパーやコンビニでも“土用の丑の日”向けの商品が多数並んでいます。
定番のうなぎ弁当のほか、牛丼や梅ごはん、冷やしうどんなど、手軽に購入できる代替メニューが豊富です。
冷凍食品コーナーでも「うなぎ風蒲焼き」「うなぎのタレ付きごはん」などのアレンジ商品が販売されており、忙しい方にもぴったり。
また、「うな次郎」という魚のすり身を使った“うなぎ風食品”も注目されています。見た目も味も本物そっくりで、価格も手頃。小さな子どもや高齢の方にも食べやすいということで、ここ数年で人気が急上昇中です。
家族で楽しむアレンジレシピもおすすめ!
「うなぎを食べる」という型にとらわれず、“う”のつく食材を使った料理を家族で考えるのも楽しい過ごし方です。たとえば「冷やしうどんに梅干しと大葉をトッピング」するだけでも、涼しげで季節感のある一品に仕上がります。
子どもと一緒に「“う”のつく食べ物を探してビンゴゲームをする」「“う”の料理コンテストをする」など、行事を家庭内イベントにしてしまえば、自然と記憶に残る体験になります。
土用の丑の日を、家族の時間を共有する日として再定義するのも、現代ならではの工夫の一つです。
「うなぎを食べない=間違い」ではない
大切なのは、“土用の丑の日”という日本の行事をそれぞれのスタイルで楽しむこと。
「うなぎを食べなきゃ!」と無理にこだわる必要はありません。むしろ、自分たちの暮らしに合った方法で「今日はちょっと特別な日だな」と思えるような過ごし方ができれば、それで充分です。
うなぎが苦手な人も、予算を抑えたい人も、自分なりの“土用の丑の日”を見つけてみてはいかがでしょうか?
現代の土用の丑の日の楽しみ方とは?
昔ながらの風習が、今の暮らしに合う形へ
「土用の丑の日」と聞くと、「なんとなく昔ながらの風習でしょ?」と思うかもしれません。
たしかにその由来は江戸時代までさかのぼりますが、現代に生きる私たちにとっても、この行事はさまざまな形で楽しめるイベントへと変化しています。
かつては「うなぎを食べて暑さに備える」というシンプルな意味合いでしたが、今では食文化だけでなく、季節を感じるライフスタイルの一部として受け入れられています。
地域のお祭りや家庭内イベント、SNSでの共有など、“土用の丑の日”は少しずつ現代的な価値観と融合してきているのです。
SNSやメディアでの盛り上がりも
最近では、InstagramやX(旧Twitter)、TikTokなどのSNSでも「#土用の丑の日」「#うなぎの日」などのハッシュタグがトレンド入りするほど、注目を集めています。
家庭で作った“うなぎ風”レシピや、“う”のつくオリジナル料理、さらにはコンビニ商品のレビューまで、バリエーション豊かな投稿があふれています。
また、YouTubeなどでは、丑の日に合わせた料理動画や食レポなども多くアップされており、行事を知るきっかけや、他人の楽しみ方を参考にする手段としても活用されています。
こうしたSNSの力が、昔ながらの行事を今の若い世代にも広げる後押しになっているのです。
商業イベントとしても大人気
スーパーや百貨店などでは、「土用の丑の日フェア」と題して、特設コーナーが設置されることも増えてきました。
予約制のうなぎ弁当、うなぎ風お惣菜、季節限定の“う”のつく食材メニューなど、まるで“夏の食の祭典”のように盛り上がります。
また、地域によってはうなぎ祭りや物産展なども開かれ、観光や商業の活性化イベントとしての一面も担うようになっています。
ただの“食文化”にとどまらず、地域や産業を元気にする行事としても注目されているのです。
家族イベントとして再注目
現代の家庭では、共働きや多忙なライフスタイルが一般的となっており、なかなか全員そろって夕食を囲む機会も減ってきています。
そんな中で、「今日は丑の日だから、ちょっと特別なごはんにしよう」と計画することは、家族のつながりを感じる良いきっかけになります。
たとえば、以下のような家族イベントはいかがでしょうか?
-
“う”のつく食材でビンゴゲーム
-
子どもと一緒に作る「うなぎ風料理」
-
家族で「今夜はうどん祭り!」とテーマを決める
-
「我が家の土用メニュー」コンテスト開催
ちょっとした工夫で、家族の会話も増え、記憶に残る1日になるはずです。
行事の意味を再発見して、暮らしを豊かに
忙しい毎日の中で、つい見落としてしまいがちな「季節の行事」ですが、こうした日をきっかけに、ちょっとだけ生活に彩りを加えることができます。
「今日は土用の丑の日か。少し丁寧にごはんを用意しようかな」
「昔の人の知恵って、面白いな」
そんな気づきがあるだけで、日々の暮らしは少し豊かになります。
行事の本質は、決して豪華なことをすることではなく、暮らしの中にある“文化”や“つながり”を再確認すること。
土用の丑の日もまた、そうした大切な行事の一つなのです。
まとめ
「土用の丑の日にうなぎを食べる理由って?」という素朴な疑問から始まり、この記事ではその歴史的背景や文化的な意味を深く掘り下げてきました。
江戸時代に平賀源内の発案によって始まった“うなぎの日”という風習は、ただの販促アイデアにとどまらず、今や日本の四季を彩る伝統的な文化となっています。
また、「うなぎを食べなければいけない」という決まりはなく、“う”のつく食べ物を自由に楽しむことで、この行事を自分なりに味わうこともできます。
梅干しやうどん、牛肉など、身近な食材で丑の日を楽しめるのも、日本の文化の柔軟さと豊かさの表れです。
現代では、SNSや地域イベント、家庭内での工夫などを通じて、“土用の丑の日”がより親しみやすく進化しています。
昔の知恵を、今の生活スタイルに合うかたちで楽しむこと。それが行事を「自分のもの」として根づかせる秘訣なのかもしれません。
今年の土用の丑の日は、あなたのスタイルで楽しんでみませんか?