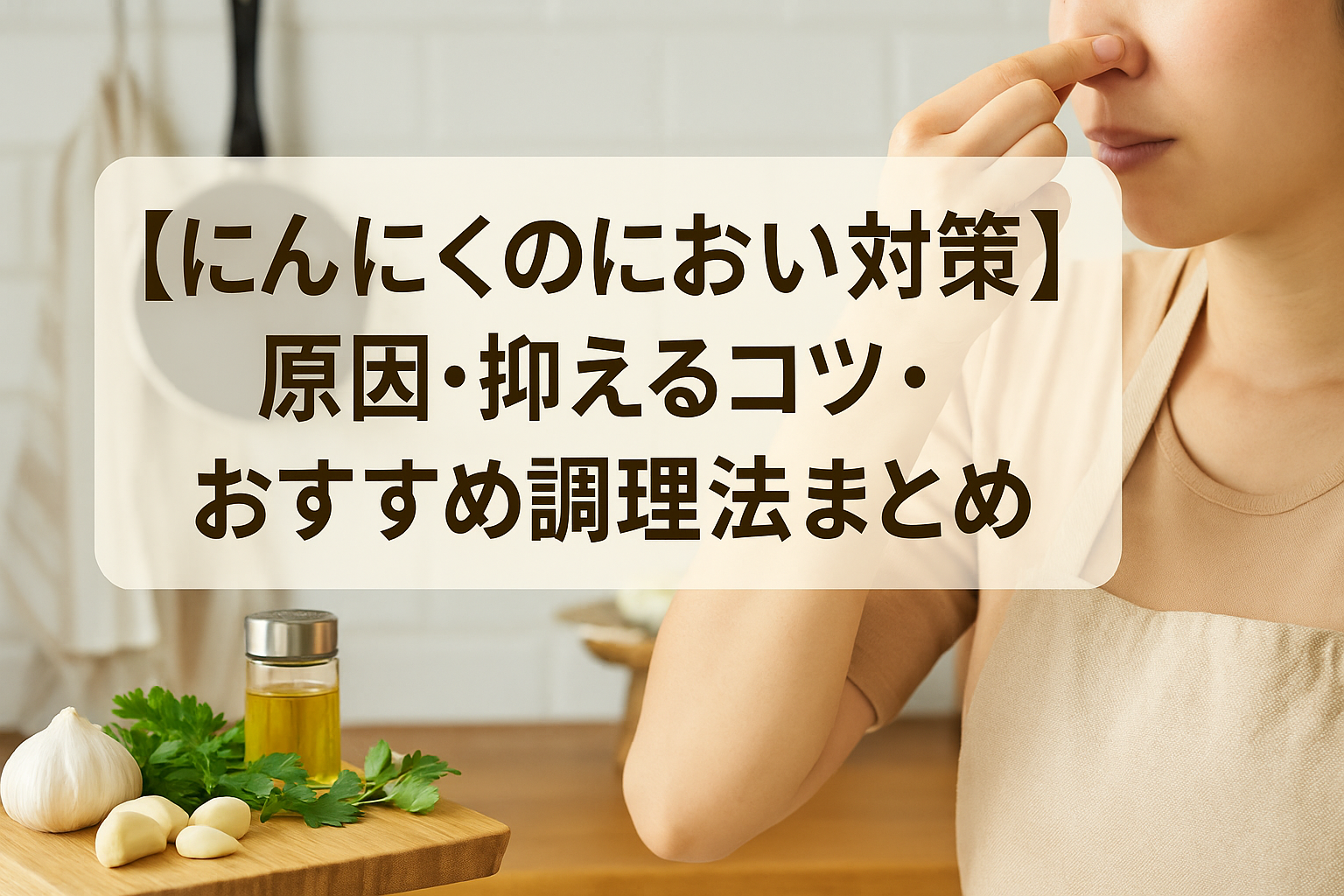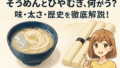にんにくは料理に欠かせない存在。香ばしい香りが食欲をそそり、ちょっと加えるだけで一気に本格的な味わいにしてくれます。でも…気になるのはやっぱり「におい」。
食べたあと、自分では気づかなくても周りから「あれ?」と思われることがあると、つい敬遠してしまいますよね。
この記事では、「にんにくは好きだけど、においが心配…」という方のために、においが発生する理由や抑えるコツ、においを気にせず楽しめる調理法などをわかりやすくまとめました。
にんにくと上手につき合いながら、もっと気軽に、美味しく楽しむヒントをたっぷりお届けします!
にんにくのにおいはなぜ発生するの?
切ると急ににおうのはどうして?
にんにくを包丁で切ったり、すりおろした瞬間にツンとした独特のにおいが広がりますよね。この現象には、にんにくに含まれる「アリイン」という成分が関係しています。にんにくの細胞が壊れると、アリインが酵素によって「アリシン」というにおいの強い成分に変化し、それが空気中に広がるのです。この反応が起こることで、にんにくは一気に香りを放ち始めます。においは強烈ですが、これが料理を美味しく感じさせる香りにもつながっているのです。
においの成分「アリシン」とは?
にんにくのにおいの中心的な役割を担っているのが「アリシン」という成分です。アリシンは、にんにくを切ったり潰したときに生まれる揮発性の化合物で、とても刺激的な香りを持っています。アリシンは空気中で分解しやすく、他の物質と反応してにおいが強くなることもあります。また、アリシンは調理方法によって変化する性質があるため、使い方次第でにおいの感じ方が大きく変わるのも特徴のひとつです。
にんにくを食べると体からにおいが出る理由
にんにくのにおいは、口の中だけでなく体全体から感じることがありますよね。それは、にんにくを食べた後に体内で作られたアリシンが、血液に乗って体のあちこちを巡るためです。最終的には、肺を通して呼気として出たり、汗腺から汗と一緒に排出されたりします。このようにして、にんにくのにおいが呼吸や汗として現れるのです。自分ではあまり感じないこともありますが、周囲に伝わりやすいので気になる方も多いようです。
どれくらいにおいが続くの?
にんにくを食べたあとのにおいは、数時間で消えるものもあれば、長ければ1日以上続くこともあります。特に生のにんにくをたくさん食べた場合は、体内に残る成分の影響でにおいが長く続きやすいとされています。個人差もありますが、平均的には食後12〜24時間はにおいが続く可能性があると考えられています。翌日の予定がある場合などは、量や食べる時間に少し気を配ると安心です。
加熱するとにおいは減るのか?
はい、加熱することでにんにくのにおいはかなり抑えられます。生の状態ではアリシンが強く香りますが、火を通すことでこの成分は分解され、においがまろやかになります。特に、にんにくを丸ごとローストしたり、ホイル焼きにする方法では、甘みが引き出され、香りもやさしくなります。ただし、調理中のにおいは立ちやすいので、換気や調理の工夫も大切です。食後のにおいが気になる方には、加熱料理がおすすめです。